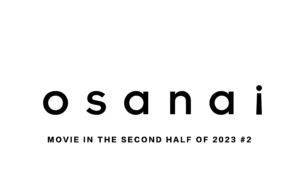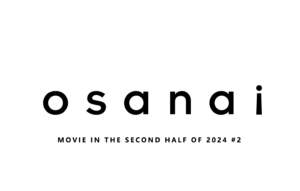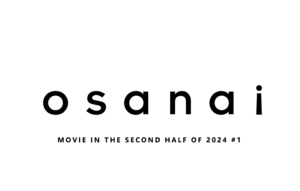ここまでに語った流れから外れた作品について簡単に触れていく。下半期の日本映画は驚異的な豊作だったと言っていい。
「キリエのうた」は岩井俊二の集大成。徹頭徹尾「エモさ」の塊のような作品。それを受け入れられる人にとっては生涯忘れがたい傑作になるだろうし、受け入れられない人にはさぞかしうんざりするような作品となるだろう。既成の映画文法に囚われず、自分の思いだけを徹底的に正直に描く作風は、「この空の花」に始まる大林宣彦の晩年の作品群を思わせる。
またこの作品は「我々にとっての戦争」とも言える東日本大震災が重要なモチーフとなっている。上に上げたような戦争ものと同列には並べられなくても、実によく似た終末感や仄暗い希望が感じられ、フィーリング的には一連の戦争ものと強く共振するものがある(そのようなフィーリングに関して言えば、少し荒唐無稽な「セカイ系」作品ではあるが、紀里谷和明の「世界の終わりから」も非常によく似た肌触りを持っていた)。
「春に散る」はボクシング映画の新たな傑作。近年の日本映画で最もハイクオリティなジャンルはボクシング映画ではないのかという仮説は、本作によって確たるものとなった。原作者 沢木耕太郎らしいロマンティシズムが若干鼻につく部分もあるが、今や俳優として絶頂期にいると言っていい佐藤浩市の演技が、そんな不満も軽くねじ伏せてしまう。
「市子」「アンダーカレント」という、「失踪」を大きなモチーフとした作品が2本並んでいるのも印象的だ。「市子」は時間軸を解体したミステリー仕立てで、1人の女性が凄惨な境遇を生き抜くための選択を描いた作品。とりわけ宮部みゆきの小説『火車』を彷彿とさせ、人間が生きることの困難さと、それを乗り越えるため犯罪に走らざるをえない姿が胸に迫る。
「アンダーカレント」は豊田徹也の大名作漫画を、今や日本映画のフロントランナーの1人となった今泉力哉が映画化した作品。原作のエッセンスを巧みに汲み取りつつ、原作にはないラストを付け加えることで、より明確な救いを提示する優しさが印象的だ。
「正欲」は、ある特別な性癖を持った人々の生きづらさを描いた作品。その性癖に対して「あんなもの大した問題ではないだろう」という意見も目にするが、それは1つの象徴でしかない。LGBTであれ何であれ、「人と違う」要素を持つことでどれほど生きづらさが増すか、とりわけそれが(まさしく「大した問題ではないだろう」といった他人事の言葉で)周りに理解されない場合どういう苦しみが生じるのかを丹念に描いている。
面白い才能として「監督 永江二朗/脚本 宮本武史」のコンビにも触れておきたい。昨年「きさらぎ駅」という低予算ホラーの傑作を放った2人が、やはり同規模の作品として作り上げた「リゾートバイト」は、前作に勝るとも劣らぬホラー映画の快作。特撮がさすがにチープすぎるという欠点はあるが、都市伝説的なホラーとして始まり、一ひねりも二ひねりも加えたストーリーによって、黒沢清の「回路」を思わせるようなラストに着地する手腕はお見事。彼らにはこの調子でどんどん新作を作りだしていってほしい。
<参考>
*1:興行成績については「映画評価ピクシーン」さんの情報を参考にさせていただきました。