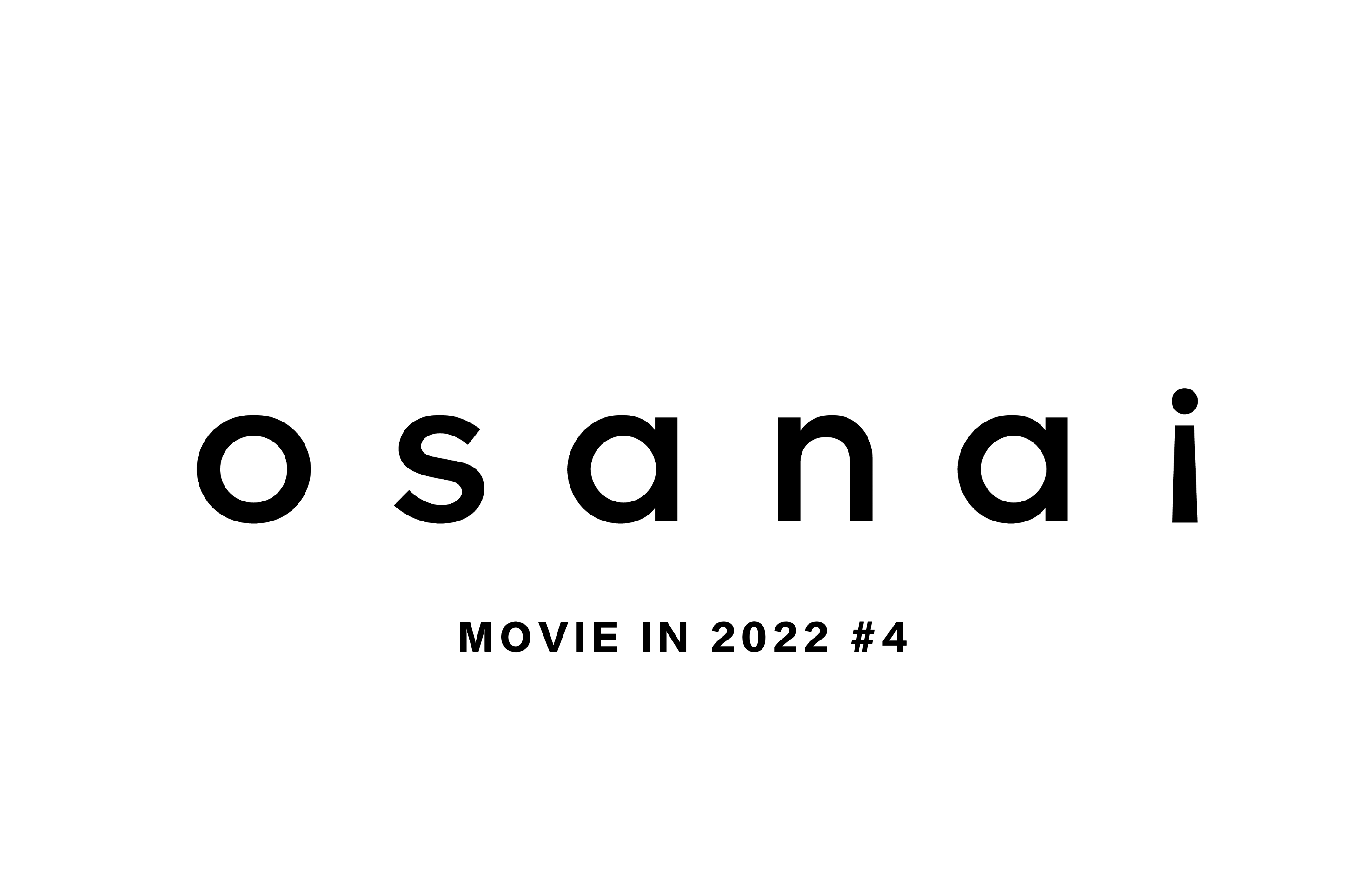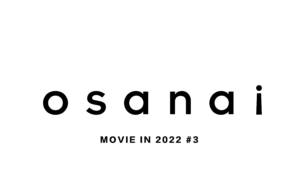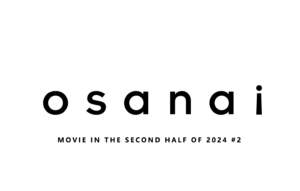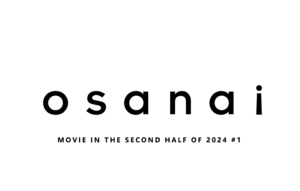映画は、何が面白いのだろうか。
みんなが「面白い」と思っているものが面白いのか。「推し」の俳優や映画監督の作品は無条件に面白いのか。それとも個人には確固たる審美眼があるもので、それぞれの視点によるそれぞれの面白さというものが存在するというのだろうか。
その辺りのプロセスや考え方は人それぞれだとして、2022年は、作り手の「つくる」という意思が伝わる作品が目立ったような印象がある。
そりゃ、たくさんの関係者を必要とする映画づくりにおいて、相応のエネルギーが必要なのは理解しているつもりだ。だが、あえて上述したのは、「つくる」という意思が伝わる作品がそのまま評価にもつながるというムードについて一考したいと思ったからだ。
*
いくつか、具体的に。
商業的には振るわなかったといわれている「ハケンアニメ!」。実はコアファンから根強く支持されているらしい。劇中で、そのまんま別映画としても成立しそうなアニメ作品がふたつも出てきて、「ああ、これはかなりの予算がかけられた作品だな」と感じることができるのは確かで。「ハケン」というものの在り方にコミットできなかった僕だけど、「ものづくり」に携わる身ゆえ、登場人物ひとりひとりの言動に、いちいち胸が熱くなれた。
メガヒットにもなった(なりつつある)、「トップガン マーヴェリック」と「THE FIRST SLAM DUNK」。
前者は、トム・クルーズによる作品への執着が話題になった。「ただの続編では意味がない」と言い放ち、自他ともに過酷なトレーニングを強いて、嘔吐も辞さない撮影を敢行した。彼らにどれほどの重力がかかっているのか知る由もないけれど、映画をつくることへの強い思いは、文字通り「痛み」を感じさせるほどに伝わってきた。
そして、現在も公開中の「THE FIRST SLAM DUNK」。1990年代の人気バスケットボール漫画を、四半世紀の時を経て、換骨奪胎作り替えてしまった。「スラムダンク好きのおっさんによるノスタルジー消費だろう」という前評判を跳ね除け、全く新しいスラムダンクが生まれてしまった。「原作ファンの期待を裏切らないように」と苦心してきたフィルムメーカーたちの不文律を壊したのは、映画監督に初めて挑んだ漫画家・井上雄彦というのも、また皮肉なものである。
体当たりの演技とか、怪演とか、俳優のパフォーマンスを過度に称賛する風潮がある。そりゃ仕事だから熱心に演技する必要はあるだろうし、怪演のほとんどが演出家によるディレクションであることは無視されているような感もあるけれど、「TITANE チタン」の主人公・アクレシアを演じたアガト・ルセルだけは特筆しておきたい。役に憑依してしまったのだが、何というか、彼女が本来有していた身体や表情の輪郭が、根こそぎ削ぎ落とされているような雰囲気を作り出すことに成功している。これが始めての演技体験だというのだから、恐れ入る。並大抵の覚悟がなければ、あれほど自分を作品に捧げることはできない。