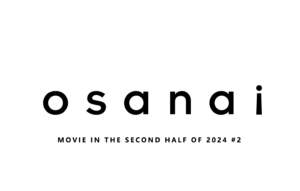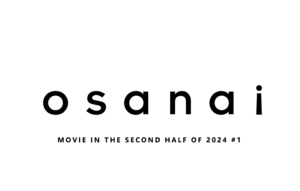父と娘の関係を描いた作品としてダーレン・アロノフスキーの「ザ・ホエール」にも触れたい。この物語の主人公チャーリーは、タイトルの通り、鯨のような272kgの巨体を抱えている。大学のオンライン講座で生計を立てている彼がこのような姿になったのは、妻と別れ恋人となったアランの死だった。アランの妹である看護師のリズだけが、チャーリーの元を訪れ世話をしていた。ある日、重度の肥満により自分の余命がわずかであることを知ったチャーリーは、長らく連絡を経っていた17歳の一人娘エリーとの再会を決意する。
しかし、久しぶりに会ったエリーは、チャーリーに対して全く心を開いていなかった。エリーはチャーリーに対して悪態をつき、彼の醜態を自らのSNSにあげる。これまで放置してきた仕返しだと言わんばかりに。だが、チャーリーはそんな態度にもかかわらず、エリーの勉強を見ることを口実になんとか彼女に歩み寄ろうとする。エリーがチャーリーに心を開かない理由は、彼の離婚にある。自ら愛を放棄しながら、再び愛そうする姿勢は、一見するとただのエゴに見える。しかし、拒絶されながらも愛そうとする姿に、思わず見入ってしまう。
カラムやチャーリーと同じく、シングルファザーの父親が登場するのが、ウベルト・パゾリーニの「いつかの君にもわかること」だ。窓拭きの清掃員として働く33歳のジョンは、若くして不治の病を患い、余命があとわずかしかない。彼には、男手ひとつで育ててきた4歳の息子マイケルがいる。マイケルの次の家族を探すために、養子縁組の手続きを行い、様々な家族と出会う。誰にマイケルを託すべきなのか。そして、「死」というものをまだ理解していないマイケルに、「死」をどう伝えるべきなのか。正解の選択肢がない中、ジョンは残された時間を過ごしていく。
「いつかの君にもわかること」は、実際の出来事に基づいた記事を読んだことに着想を得てつくられている。パゾリーニ監督はそれを映像で表す上で、できるだけセンチメンタルにならないように気をつけたという。実際に、養子縁組候補との何気ない会話や、マイケルとのささやかな日常、ジョンのちょっとした表情の変化から読み取れる苦悩など、日常の中で確かにそんなシーンがありそうだという要素で構成されている。
余命わずかな者と残される者という構造は、これまでも多く描かれてきた題材だ。しかしこれまでと異なるのは、涙を誘うようなセンシティブさやドラマチックさがないこと。もしかしたら、今隣で座っている人も、ジョンのような悩みを抱えているのかもしれない。そんな観る者の想像力を刺激する。
体格も良いジョンの見た目は、余命があとわずかであるという弱さを感じさせない。「いつかの君にもわかること」も前の二作品と同様、「父親=強い」という固定観念から距離をおいた作品のように思う。