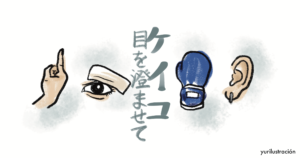性加害は「決して許されない」もので、「被害者は何も悪くない」
本作は、「なかったこと」にされがちな性的暴行事件に真っ向から向き合っている。だが決して、“男性vs女性”の物語ではない。性被害を憎んでいるのは、女性だけではない。
本作に登場するNYタイムズ紙の編集長・ディーン・バケットは男性である。彼は、外部からかけられる陰惨な圧力から記者たちを守り、必要な助言を怠らず、的確なタイミングでゴーサインを出した。
「書け!」
ディーンが毅然とそう言った場面では、胸が震えた。彼は紛れもなく、性暴力を憎んでいた。こんなことは終わりにしなければと、そのために何が何でも記事を世に出すのだと、揺るぎない使命感を抱いていた。
ディーンだけではない。ミーガンとジョディそれぞれの夫は、妻の意思を理解して献身的に家族を支え続けた。ワインスタイン・カンパニーの財務会計を担当していたアーウィン・ライターは、女性たちの被害を知り、彼女たちの声に具体性を持たせるべく大きな決断をした。
性別に関わらず、誰もが性被害の被害者にも加害者にもなり得る。本作で描かれている被害者は女性で、世界的に見ても女性が圧倒的に被害に遭いやすい現実は否めない。しかし、イコール男性全てが性加害者ではないし、性加害を容認しているわけでもない。性別による分断は、課題解決から遠のくばかりか、要らぬ争いを生む。本当に必要なのは、起きた問題にどう対処すべきかを見極める判断力だ。本作は、それを考える上で重要なエピソードが詰まっている。
正しく問題にあたるためには、まず、知ることだ。被害者の声を聴くことだ。そこから全てがはじまる。
そのためにも、フラットな気持ちで本作を鑑賞し、性犯罪における課題に向き合う人が、一人でも増えてほしいと切に願う。「女だから」「男だから」ではなく、「一人の人間として」問題に向き合う。その意識を、今一度取り戻すべき節目にあるのではないだろうか。
「変えなければいけないもの」がある。そのためには、「いつか変わる日が来るのを待っているだけ」では足りない。どんなに小さくとも、できることを積み重ねていくしかない。
私にとってそれは「書くこと」で、ミーガンとジョディの信念と通ずるものを感じた。彼女たちもまた、取材を通して知り得た事実の一つひとつと丁寧に向き合い、真実を語ることは物事を変える力があると信じた。そして同じくらい、現状を変えるべく声を上げた女性たちの勇気があったからこそ、社会に一石を投じることができたと私は思っている。
しかし、声を上げるのは、被害者の責務では決してない。
多くの苦痛をもたらす二次加害に晒されながら、被害者が声を上げなくても済む社会。それこそが、本来の正しい姿であると思う。何より、性加害は「決して許されない」もので、「被害者は何も悪くない」という当たり前のことが、全世界の共通認識であってほしい。
現行法の改正に伴い、日本国内でも「性的同意の有無」を論点として、日々論争が繰り広げられている。それらを見るにつけ、論争の軸にあるものが「被害者の声」ではないように思えて、あまりにもやりきれない。
#MeToo
このハッシュタグを用いて、今もなお、大勢の被害者が身を切られるような痛みを堪えて声を上げている。
その声を、どうか「ないもの」にしないでほしい。ミーガンとジョディのように、小さな声ほど真摯に拾ってほしい。
被害者の声が踏み潰されない世界。
それを作ることができるのは、一人ひとりの誠意と信念だ。それらは“目に見えない”けれど、その力を信じて本作が創られたのだと、私は思いたい。
──
■SHE SAID/シー・セッド その名を暴け(原題:SHE SAID)
監督:マリア・シュラーダー
原作:ジョディ・カンター、ミーガン・トゥーイー『その名を暴け─#MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い─』
製作総指揮:ブラッド・ピット、リラ・ヤコブ、ミーガン・エリソン、スー・ネイグル
製作:デデ・ガードナー、ジェレミー・クライナー
脚本:レベッカ・レンキェヴィチ
出演:キャリー・マリガン、ゾーイ・カザン、パトリシア・クラークソン、アンドレ・ブラウアー、ジェニファー・イーリー、サマンサ・モートン、アシュレイ・ジャッドほか
配給:東宝東和
(イラスト:Yuri Sung Illustration)