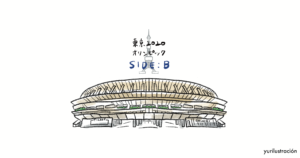フランス・パリの高層住宅が連なる再開発地区である13区。アジア系移民も多く暮らす場所で、男女4人が不思議に混じり合う。全編モノクロによる「新しいパリ」を描いた物語。
「ディーパンの闘い」「預言者」のジャック・オディアールが監督、脚本を務める。共同脚本として「燃ゆる女の肖像」のセリーヌ・シアマ、「アヴァ」のレア・ミシウスが参画。グラフィック・ノベル作家のエイドリアン・トミネの短編集の3作品が原案となっている。
──
人が人を愛するとき、内側に生まれる感情はきれいなものだけではない。ヘドロのように濁った感情もあれば、寒々しいほどに空虚な感情もある。誰かを愛し、愛される過程は、美しい物語だけにとどまらない。それが成立するのは、御伽噺の中だけだ。
先日、ミニ・シアターにて「パリ13区」を鑑賞した。作品に登場するのは、パリに住まう4人の若者たち。彼らは、それぞれが誰かに恋をしていた。恋は、人を愚かにする。愚かで、不器用で、だからこそ美しい。そんな大人たちの姿が、アジア系移民が多く暮らすことで知られる多国籍街、13区を舞台に描き出される。
物語序盤、ルームシェアを希望するカミーユが、祖母のアパートで暮らすエミリーのもとを訪れる。「ルームシェアは同性を希望する」と最初は断るエミリーだったが、他愛ない会話を通して惹かれ合った二人は、会ったその日にセックスをする。
エミリーは、体を重ねるごとに愛情を深めていくタイプで、自他の境界線が曖昧だ。対してカミーユは、セックスと恋愛を明確に線引きする。その境界線の引き方は、冷徹ともいえるほどだ。対局にある二人。それゆえ、すんなりと「恋人」に発展しない関係性は、背中が疼くようなじれったさを感じる。どんなに体を重ねても、深いところでは決して交われず渇望する心。そのやるせなさが、少しずつエミリーの自制心を奪っていく。
カミーユは、エミリーの気持ちに気づきながらもそれに応えようとはしない。それどころか、ルームシェアの自室に同僚の女性を連れ込み、セックスに及ぶ始末だ。
好きな異性が他の女性と行為に及んでいる音を聞いたことがあるだろうか。私は、ある。あの音は、拙い理性を容赦なく夜の闇へと手招きする。
苦痛極まりない音に耐えきれず、エミリーは電話で姉に助けを求める。しかし、「そんなことで夜中に電話してこないで」と拒絶されてしまう。「”そんなこと”なんかじゃない」と、見ているこちらが叫びそうになった。エミリーの不安定な感情曲線を通して表現される恋のもどかしさは、リアリティにあふれている。それゆえ、観ているこちらまで容易く引きずり込まれる。バスルームで泣きじゃくるエミリーは、濡れネズミのように無様で、そんな彼女の姿が在りし日の自分と重なった。届かない想いを持て余す夜は、慟哭しても尚、消化しきれるものではない。
この夜を境に、エミリーは感情の起伏をより露にする。嫉妬の感情は、表に出す側も出される側も、ひどく消耗する。ねじれた好意を押し付けられるほどに、加速度的に冷めていくカミーユの気持ちも理解できなくはない。恋は、人から理性の手綱を奪う。「言わなければいい」「やらなければいい」とわかりきっていることを、なぜか実行してしまう。もがき、喘ぎ、壊し、すがりつく。体の関係からはじまった不器用な恋の行方は、その後登場する二人の女性、ノラとアンバー・スウィートの人生と複雑に交錯していく。