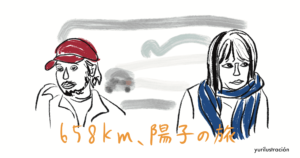レオにとって、レミはまさにそういう存在になっていった。クラスメイトの揶揄いによって深く傷つき動揺したレオは、徐々にレミと距離を置くようになってしまう。まるで一卵性双生児のように、ふたりきりの世界に閉じこもっていたレオとレミは、ありのままで居続ける限り社会に迎合されない。レオはそのことに気づいて、ひどく狼狽する。すぐさまその先の排斥と迫害を想像し、レミを遠ざけたレオを、ぼくは責め抜けない。だれも責め抜いてはいけない。
翻って。レオやレミと同じく、あれほどべたべたひっついてふたりだけの世界を構築していたぼくとMが似た揶揄いを受けなかったのは、あの年代の「女の子」特有の「ニコイチ」文化があったからだろう。お揃いの服を着たり、お揃いのものを所持したりして、「ふたりで、ひとつ」を過剰にアピールする「女の子」たちは、「男の子」たちに課せられる重圧からは自由だ。もちろん「女の子」たちもまた、そうせねば生き抜けぬほどの別の重圧を負わされているからこその現象でもあるが。
かつてふたりだけに通じる合図を持ち、ふたりだけの秘密基地を持っていたレオとレミ。洞窟の中で「戦いごっこ」をする彼らが交わす言葉は、まるで双子語のようだ。その世界を、その言語を、レオは破壊してしまう。ふたりでいたときには自然でいられたのに、集団に帰属した途端、そう在れなくなる。さらに同級生たちよりも小柄で華奢なせいか「オンナオトコ」「お嬢ちゃん」などという言葉で揶揄われがちだったレオは、それを払拭するようにアイスホッケーを始める。肉体がぶつかり合う激しいスポーツを選んだのは、「男らしさ」を強調するためだろう。
集団へ迎合しようともがき、真に大切な存在を蔑ろにするレオ。レミはそんなレオの変化に、戸惑い、傷つき、憤る。同じベッドで寝ることを拒否され、自転車で並んで通学路を走ることを嫌がられるレミは、レオとは対照的に「これまでのふたり」を優先させようともがく。他者からの視線よりも、レオのほうがずっと大事だから。しかしレミがもがけばもがくほど、レオもまた苦しむ。そしてとうとうレオの拒絶に耐えられなくなったレミは、この世を去る。
それからレオの、長い長い苦しみが始まる。家族ぐるみで親交のあったレミの両親とは、彼の死後も交流が続いていく。ふたつの家族がテーブルを共にした夜、レオの兄が「未来」を語る。自分の将来像、卒業後の夢。それを聴いたレミの父親が堪えきれずに泣き出してしまうのは、彼の息子の口から「未来」が語られることはもうないからだ。
一方で、レミの母・ソフィは悲壮感をあらわにしない。毅然としているとか、あるいは冷たいとか、そんなんじゃない。ただ置いてけぼりにされているようだった。突然いなくなった息子、探しても探してもその理由が見つからない。愛する息子が何ひとつ遺してくれなかった事実を前に、ソフィは立ち尽くしていた。死んだひとの気持ちなんて、もうわからない。知りようがない。だって、本人にはもう訊くことが叶わないんだから。ソフィだってそんなこと、痛いほどわかっている。それでも「なぜ」が頭の中をぐるぐると駆け巡る。だからソフィは、悲しげな微笑を浮かべるしかできない。
そのソフィのほほ笑みを、レオは追いかけ続けることになる。レミの荷物を学校に引き取りに来たときも、葬式でも、自らの練習風景を見に来てくれたときも、いつだってレオはソフィを目で追ってしまう。言わなければ。でも、なんて?言ったら自分は、どうなってしまう?小さな心が罪の意識に苛まれていく様子は、あまりに酷だった。