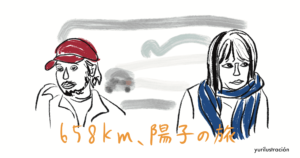主人公のレオとレミは、幼馴染で大親友。いつどんなときも、なにをするにも、必ず一緒だ。しかしながらその親密さは、成長に伴い周囲から奇異の目を向けられることとなる。中学校に入学したふたりは、入学初日も隣に座ってひそひそ声で内緒話をする。ぴったりと体を寄せ合うことも、相手の肩に頭を乗せることも、ふたりにとってはごく自然な行為で、ごく普通の日常だ。
けれども周囲はそう捉えない。ホモフォビアという名の好奇心に満ち満ちた目で、新たなクラスメイトたちはふたりをじろじろと眺める。舐めるようなあの視線。意地の悪い笑みを浮かべるそのうちのひとりに、過去のぼくの加害者を重ねて比喩ではなく死にたくなった。あえて強烈な言葉を使うが、嘲笑は人を殺すのだ。
入学して数日後だろうか、不意にクラスメイトの女の子たちから「あなたたちってカップル?」と訊ねられる。レオとレミはさっと顔色を変えるが、女の子たちはなおも「いつもべったりしているから」と突っ込む。「親友なんだから当たり前だ」、そうレオが毅然と言い返しても、彼女たちは執拗だった。「それ以上に見える」と半笑いで言う女の子に、レオは「そうだ、兄弟みたいなものだ。だいたい君たちだっていつもべったりじゃないか」と反撃を試みる。でも彼女たちは意に介さない。「そうなの、私たちってラブラブなの」とかなんとか言って、ふざけていちゃついて見せる。「この話は終わり」とレオが切り上げても、「はいはい、じゃあ付き合ったら教えて」と攻撃──自覚はつゆほどもないのだろうが──をやめない。
胃が痛い。キリキリと痛む。あの女の子たちの言う通りだ。この社会ではなぜか「女の子同士」が四六時中べったりひっついていても、それがティーンズであればなおさら、すぐに同性愛と結びつけられることはない。ぼくとMのように。けれども「男の子同士」となると話は違う。レオがレミの家に泊まるとき隣に敷かれた布団ではなく必ず同じベッドで体をぴったりくっつけて眠っていることを、もしクラスメイトたちが知ったら即座に「ゲイ」と認定するのだろう。
ホモフォビアはもちろんのこと、レズビアン・カップルにだって向けられる。それは大前提として書いておきたい。ゲイカップルと比較することでレズビアンの女性たちが受けた差別を矮小化するつもりは一切ないし、ぼくがそういう思想に強く反対していることは明記しておく。ただ10代という特殊な時代において、見られ方に違いがあることは明白だ。事実、ぼくもMも、周囲から「付き合ってるの?」とはついぞ訊かれなかった。
この違いは、家父長制における「有害な男らしさ」に起因するものだろう。女をモノにしてこそ、稼いでこそ、強くあってこそ、自立していてこそ、「男」である。ジェンダー・ロールが首を絞めるのはなにも女性たちやクィアに限らない。この社会に順応できない一部のシスヘテロ男性もまた、窒息しそうになっている。その一部の男性のうち、より苦しむのは「有害な男らしさ」を内面化してしまっているひとたちだ。「男らしくない」とされる自らの気質がコンプレックスとなり、しばしば鬱屈した感情はより弱者に向けられる──女性とか、クィアとか、あるいは自分を「男らしくない」存在たらしめる“だれか”に。