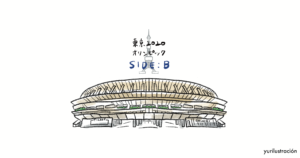人と人との出会いは、偶然と必然が絡まり合っている。性別も年齢もタイミングも関係なく、出会うことで生まれる何かに、強烈に引き寄せられる。それは、「運命」なんていう安直な言葉で表現できるものじゃない。出会うしかなかった――自身の体験においても、そう感じる場面に時々遭遇する。この作品で描かれる人間模様も、まさにその類であった。
作品のラストシーンにおいては、ほのかな光を感じた。
意地を張り、歪んだ態度と言葉でしか表現できないエミリー。スマートな振る舞いの奥に寂しさを秘め、いつもどこか満たされないカミーユ。互いの埋められない穴を持ち寄り、散々回り道をした二人は、ようやく本音を伝え合う。その際、彼らが選択した言葉は、実に簡素なものだった。時として、簡潔で平易な言葉ほど、人の胸を打つ。人と人が深くつながるために必要なものは、実はそんなに多くない。人の心は複雑で、だが、とても単純だ。
花の都、パリ。その名を聞いて私が思い浮かべるのは、芸術的な建造物や華やかな都会の暮らし、古都の威厳あふれる街並みであった。しかし、本作を鑑賞して、そのイメージは呆気なく拭い去られた。パリの顔は、ひとつだけではない。考えてみれば当然のことだ。私が現在住んでいる都市も、以前住んでいた街並みも、さまざまな顔を持っている。街を作っているのは、そこに住む一人ひとりの住人たちだ。誰がどんな角度から眺めるかにより、街の風景は変わる。匂いも、色合いも、音も、空気も。淡々と過ぎる日々の風景と、時々起こるドラマチックな出来事。これらに明確な境界線はなく、常に生活と地続きである。
本作では、パリの街並みがモノクロで表現されている。鮮やかな色彩が排除されることで、人々の生活やそこにまつわる雑多な感情が、よりリアルに生々しく迫ってくる。芸術的でも、華やかでもない。個性はあれど、どこにでもいる人たちのどこにでもある出会いと別れ。その先に続く道のりに希望があらんことを願い、スクリーンを後にした。真夏の炎天下の空は、私がパリを旅している間に、見事な夕焼けに包まれていた。
現実は、モノクロじゃない。色があり、流れ行く風景は一切カットされることなく、ただありのままに横たわり続ける。車窓から差し込む橙色の光に目を細めながら、モノクロのパリに思いを馳せた。これまで出会った人たちと、別れた人たちの顔を思い浮かべながら。
──
■パリ13区(原題:Les Olympiades)
監督:ジャック・オディアール
脚本:ジャック・オディアール、セリーヌ・シアマ、レア・ミシウス
原作:エイドリアン・トミネ『アンバー・スウィート』『キリング・アンド・ダイング』『バカンスはハワイへ』
音楽:ローン
製作:ヴァレリー・シェアマン
出演:ルーシー・チャン、マキタ・サンバ、ノエミ・メルラン、ジェニー・ベスほか
配給:ロングライド
(イラスト:Yuri Sung Illustration)