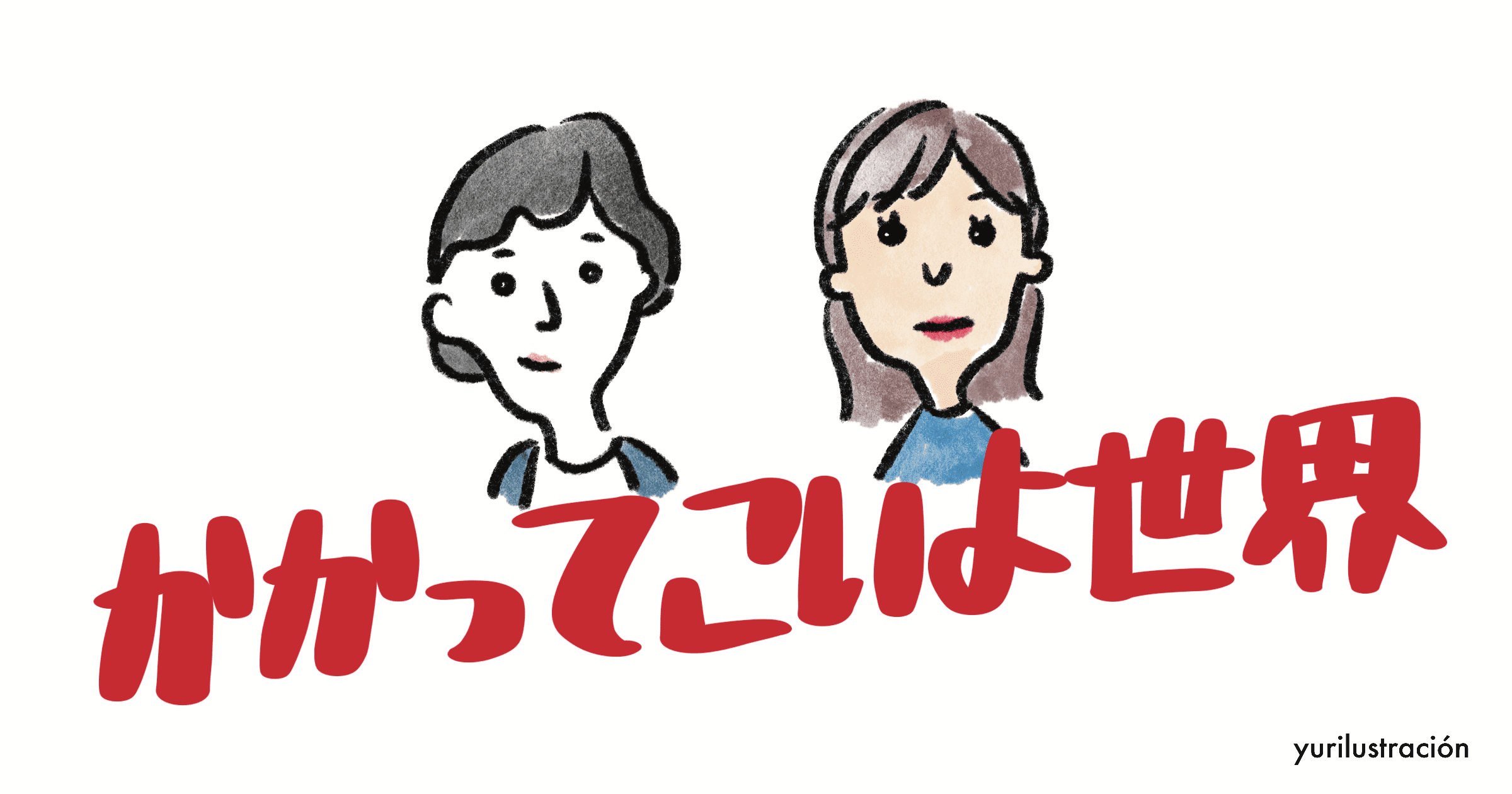脚本家を目指す浜田真紀は、バイト先の居酒屋で映画配給会社に勤務する新井国秀と知り合い、意気投合する。しかし国秀が自らを在日韓国人3世であることを告げると、ふたりの関係は微妙に変わってしまう──。
主人公・真紀を佐藤玲、国秀を飛葉大樹がそれぞれ演じる。監督は短編「触れてしまうほど遠い距離」の内田佑季。本作は脚本・畠中沙紀の実体験に基づいている。
──
内側がえぐられて、すぐには向き合えなかった
差別。炎上。いじめ。テレビを見ても、SNSを見ても、嫌なニュースばかりが目立つ。人は、誰かの上に立ち、下だと見なす者を傷つけないと生きていけないのだろうか。怒りより先に、恐怖を覚える。
ニュースの中の出来事を、決して他人事にしてはいけない。わかってはいるけれども、真正面から直視するのは簡単ではなくて、どうしても少しだけ目を背けてしまう。そして、いつも後ろめたい気持ちがつきまとう。
今回鑑賞した映画は、「かかってこいよ世界」。
「差別をされた人」ではなく「差別をした人」の心に着目した作品だ。
差別という問題に対し、目を背けることなく、向き合わなくてはならない。そう予感したが、それでもなお私は、あまり覚悟が決まらないまま映画館へと向かった。
ガリガリ。ザッ、ザッ。グツグツ。鑑賞後、どこからか嫌な音が聞こえるようだった。自分の内側がえぐられる音。もちろん比喩だけれども。
でも、それくらい私は、混乱していた。
エンドロールとともに土屋アンナさんの主題歌「Atashi」が流れる。アップテンポな音楽は、作品のエネルギーを増長させるばかり。H列14番に座る私に、思考を整理させる余地を与えてくれない。
まさに「かかってこいよ」と言われているようだった。それは世界に対してのメッセージにも聞こえたし、私に対する焚きつけのようにも聞こえた。けれども、私はなんだか圧倒されてしまって、まだ作品とうまく向き合えなかった。今になって振り返ってみれば、つくり手たちの強い思い、作品のエネルギーを感じながらも、問題に目を背けてきた自分と対峙することが怖くて、気持ちがぐちゃぐちゃになっていたのだと思う。
映画館から外に出る。8月の終わり、むわっとした暑さの残る、夜の新宿。私の内側よりも混沌とした街を歩くうちに冷静になってきて、少しずつ思考がクリアになっていった。