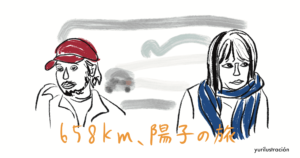でも、本当にレオが悪かったのだろうか。本当にレオのせいでレミは死んだのだろうか。
だって、レオにはああする以外自分を保つ方法などなかった。自らの意志に反して勝手に他者から性的な目で見られる苦痛は、あの年頃の子どもにとって比喩でなく地獄だ。じゃあ、本当に悪いのは?ふたりの関係を執拗に問い詰めた女子たち?それともレオを揶揄ったクラスメイト?
いいや、違う。その正体は、社会に蔓延るホモフォビアだ。家父長制に由来する「有害な男らしさ」だ。クラスメイトに責任がないとは、もちろん言わない。ただ13歳の、まだ大半が「恋」というものに対して漠然としたイメージしか持っていない子どもが、あれほどまでにレオとレミの関係を面白おかしく解釈していたのは、彼ら/彼人ら/彼女らの周囲の大人たちの思想が多分に影響しているからだ。男同士でイチャイチャしているのはおかしいし気持ち悪い。女の子同士なら微笑ましいけど、ティーンズになってまで、ああもべったりな男の子ってどうなの?こんな具合に。
レミがいなくなってから、クラスでは定期的にカウンセリングが行われるようになる。クラスメイトのひとり、レオとレミを揶揄っていた生徒がレミについて「いつもハッピーだった」と答えた瞬間、レオは激昂する。「何を知っている?」と。それでもなおもにやにやと薄笑いを浮かべる──あるいは当惑した誤魔化し笑いだったのかもしれない。ただぼくには、そしておそらくレオには、そう映った──クラスメイトを睨みつけ、レオは教室を飛び出す。
レミを喪失したまま、月日は流れていく。レミがいなくとも、レオの世界は滞りなく廻り続ける。
レオとレミが互いに抱いていた親密さは、果たして恋愛感情だったのだろうか。それはこの物語で明かされない。いなくなってしまったレミの気持ちだけでなく、レオの気持ちも。というより彼らの年齢を考慮すると、まだ定義づけるのは彼ら自身にとって難しいのかもしれない。ただそれが恋であれ、親愛であれ、何であれ、等しく尊い愛だったのには変わりない。