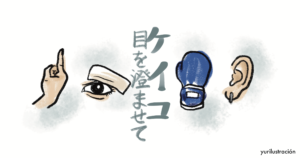崇高な料理に中指立てる“わかってないやつ”
創作の世界では、何を作ったかよりも誰が作ったかを重要視することがある。
それはもちろん、その人がこれまで積み上げてきた文脈によるところの評価なのだが、そんなことを知らない人ほど「これのどこがいいかわからない」と率直に言えたりする。
界隈の人からすると「これだからわかってないやつは……」と、冷笑されるその「わからない」の中には、作品の価値そのものを問う力が秘められている。
マーゴも“わかってないやつ”だった。貧しい環境で育ってきた彼女は、いわゆる「高級料理」を食べた経験がなかった。たばこを吸い、料理の機微には無頓着だ。
でも、マーゴだけが常に料理そのものと向き合う態度を貫いていた。
コース料理が運ばれる中で、最初に不穏がたちこめた料理が「パンのないパン皿」だった。パンをつけるソースが並ぶその皿には、肝心のパンがないのだ。スローヴィクは当然のように説明する。パンは庶民の食べ物として親しまれてきたから、お金持ちのみなさまには必要ないと。
招待客たちはとまどいつつも、これがスローヴィクの芸術だと都合よく解釈し、ありがたがるようにソースだけを食べていた。作り上げられた世界観を壊さないように、その世界の一員として必死に振る舞おうとする姿が滑稽だった。
マーゴだけが「食堂は料理を出すべきだ」と、その料理に手をつけない。タイラーは駄々をこねるなとマーゴを諌め、スローヴィクは完璧な料理の何がいけないのかと問うが、マーゴは一貫して態度を変えない。
マーゴはスローヴィクの名声も予約のとれないレストランも関係なく、“料理”を食べにきたからだ。
“わかってるやつ”のいきつく先
旅行に行って有名な建造物や美しい自然、おいしい特産物を写真に収めていると、わたしはただ写真を撮りにこの場所に来たのかと戸惑う時がある。いま、目の前にあるものを、五感をもってちゃんと受け止められているだろうかと不安になるのだ。
ホーソンでは、料理の写真を撮ることを禁止していた。目の前の料理を味わってほしいからだ。
インスタ映えが世を席巻していた頃は、見た目が派手な料理の写真だけ撮ると満足し、肝心の料理には手をつけないという問題が発生していた。
食べることは、もはや生きるためを通り越して、娯楽になりすぎている。
コース料理が進むごとに、スローヴィクの苦悩があらわになる。
芸術まで昇華した己の料理を、ステータスや情報として食べれらているやるせなさ。料理の価値をわかっていない人のために、命を削って料理を作る虚しさ。
提供される料理は、そんなスローヴィクの怒りと憎しみに比例するように、どんどん狂気をおびていく。
その中で、唯一スローヴィクの料理の価値をわかっているのはタイラーのようにみえた。どれだけ狂った料理を出されようが、客たちが取り乱そうが、目の前にある料理を心の底から堪能し、スローヴィクに気に入られようと振る舞っていた。だが、実は一番料理を貶めている者として、スローヴィクに地獄に落とされることになる。
隠し味を言い当てて得意になり、バシャバシャと料理を隠し撮りしていたタイラーこそ、料理を「情報」としてしかとらえていなかったのだ。