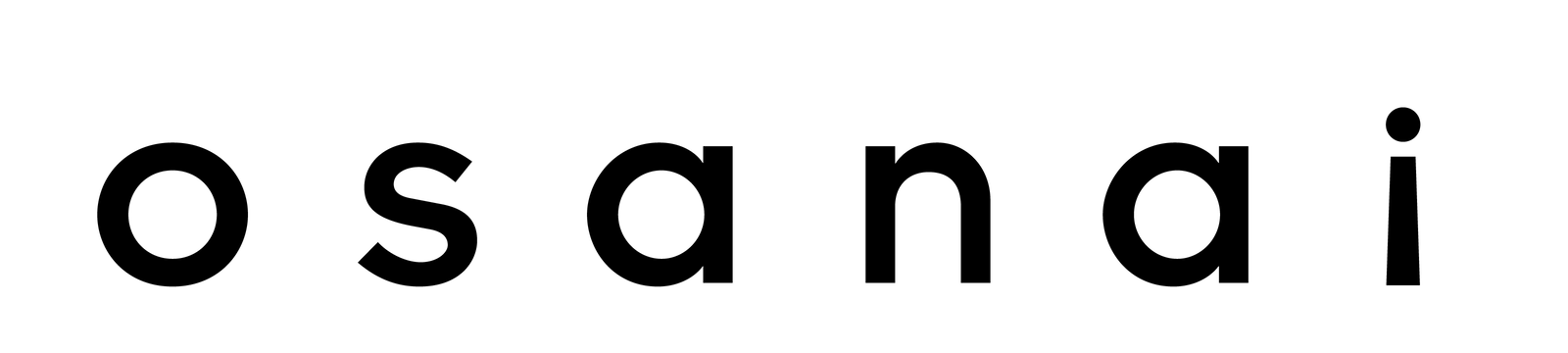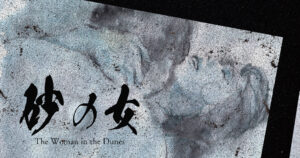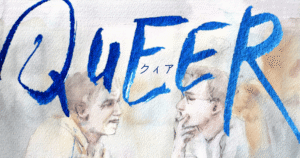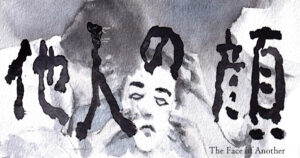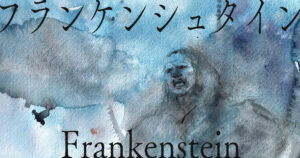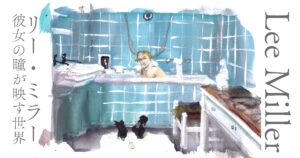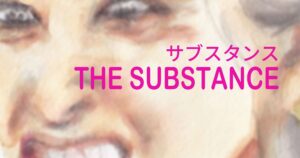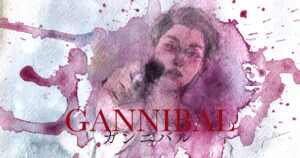映画はフィクションだが、現実と地続きで横たわっているものがたしかにある。
私の息子たちはすでに高校生と小学生になり、夜泣きも、激しい癇癪も、イヤイヤ期も過ぎ去った。自分で着替えてご飯を食べ、トイレで排泄をして、元気に登校し、夜はひとりで眠る。私の子育ての過渡期は終わった。だから今、あの頃を冷静に振り返ることができる。
マーロは私だった。あるいは、何らかの事件の当事者だった可能性も捨てきれない。「自分に限って」など、口が裂けても言えない。朝も昼も1時間おきに泣きわめく長男を抱きながら、脳内で何度も良からぬ想像をした。
息子たちを愛している。彼らを産んでよかった、会えてよかったと心から思っている。同時に、私も叫んだのだ。学校の駐車場で叫んだマーロのように、何度も何度も叫んだ。どちらも私で、どちらも母親のリアルで、決して切り離せない両者が私の中に混在している。
「俺はもう逃げない」
映画のラストで、マーロの夫・ドリューは、謝罪と共にこう言った。子育てから逃げたかったマーロ。ずっと逃げ続けてきたドリュー。2人がようやく同じスタートラインに立ったところで流れるエンディングは、優しいサウンドが耳に残る。
命を育む仕事は、尊く、険しい。日々闘う母親はいつも必死で、張り付けた笑顔の下で悲鳴を押し殺している。幸福な瞬間もたしかにあるだろう。だが、「助けてほしい」と思ったことのない母親は、おそらくいないはずだ。
母親は高性能AIではない。ただの人だ。完璧じゃなくていい。理想通りになんてできなくていい。我が子の寝顔を見ながら、「今日も無事に生きてくれた」と安堵できたなら、それだけで十分だ。
幼いジョナがマーロを抱きしめたように、母親自身が己を抱きしめられたら、と思う。私たちはあまりにも、自分に厳しすぎる。抱きしめて、「大好きだよ」と伝えて、丁寧にケアをする。我が子に向ける愛情と同じぶんだけ、自分を慈しむ。母親にそんな時間と心の余裕がある社会を。そう願うことが“贅沢”だなんて、私は思わない。
敬愛する西加奈子さんの小説『夜が明ける』(新潮社)に、こんな台詞がある。
苦しかったら、助けを求めろ。
(西加奈子(2021)『夜が明ける』、新潮社、 P380より引用)
苦しかったら、どうか躊躇わずに助けを求めてほしい。誰かのSOSを受けたら、後回しにせず動いてほしい。「助けてほしい」と声を上げることは、大変な勇気がいる。その勇気を、どうか潰さないでほしい。家族、友人、行政、もっといえば「国」そのものに、きっとできることはある。
誰もがマーロになり得る。そのことを胸に置き、現実に起きた事案についても考え続けたい。どうすれば救えたのか。どうすれば間に合ったのか。
「どうせ間に合わない」と諦めるのではなく、間に合わせる方法を模索し続ける。それこそが、私たち大人の責務であると思う。
──
■タリーと私の秘密の時間(原題:Tully)
監督:ジェイソン・ライトマン
脚本:ディアブロ・コディ
撮影監督:エリック・スティールバーグ
編集:ステファン・グルーブ
衣装デザイナー:アイーシャ・リー
音楽:ロブ・シモンセン
出演:シャーリーズ・セロン、マッケンジー・デイヴィス、マーク・デュプラス、ロン・リヴィングストン、アーシャー・マイルズ・フォーリカ、リア・フランクランドほか
配給:キノフィルムズ
公式サイト:http://tully.jp/
(イラスト:水彩作家yukko)