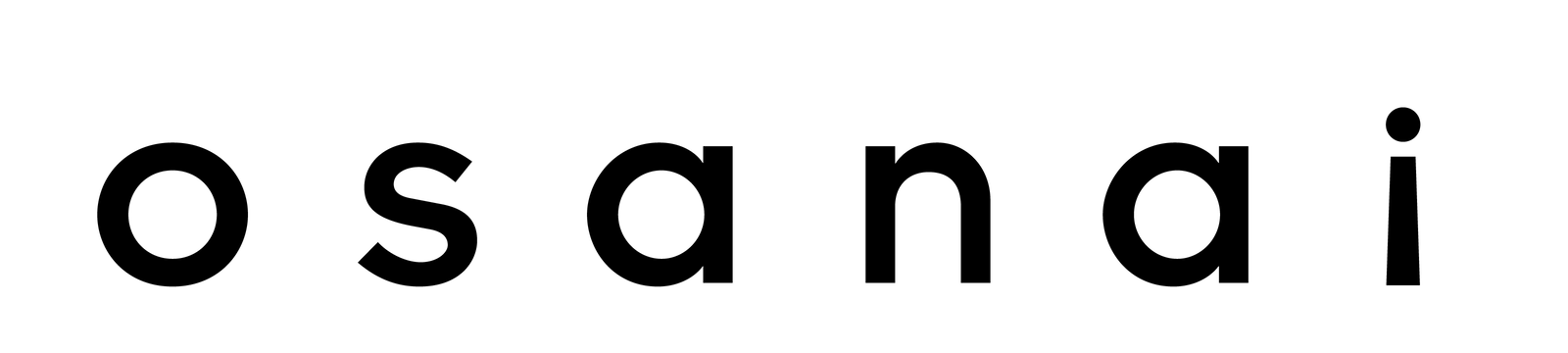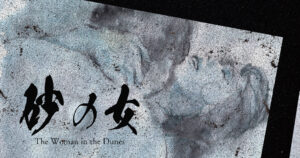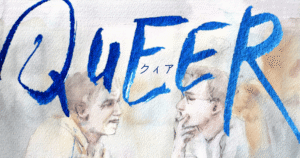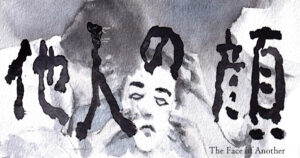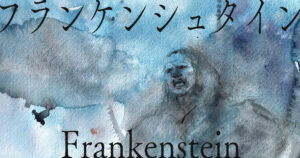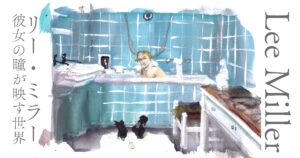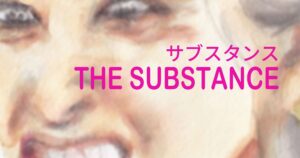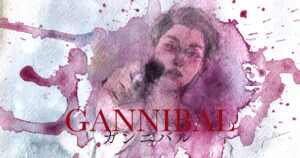育児の悩みを相談する窓口として児童相談所が広く知られるが、一般的には児童相談所への連絡は心理的ハードルが高い。その壁を超えて相談した時点で、すでに限界を超えている母親は多かろう。しかし、児童相談所のマンパワー不足は深刻で、相談を受けた当日に対応策を講じるのは、余程の緊急事態でなければおよそ不可能だ。人員不足は国の責任であり、地域に根ざす事業所が自力でどうにかできる問題ではない。
産後うつに関する知識や、予防に役立つ環境調整の必要性が、世間に正しく認知されていない点が大きな問題であると私は思う。産後うつは、“気の持ちよう”で解決するような疾病ではなく、「出産でナーバスになっているだけ」と軽く捉えるのは誤りだ。
本来ならば、出産前から産後うつの予防に備えるのが望ましい。そのためにも、国の支援体制の充実や、企業における男性の育児休暇取得率向上は急務である。父親の育児休暇申請の可否が企業の体質によって左右される社会では、産後うつの予防などできようもない。社会のあり方が抜本的に変わらなければ、この先も同じ悲しみは繰り返される。
子育てはさまざまな要因が複雑に絡み合っており、母子の健康状態や基礎体力、発達特性や障害の有無、頼れる親族が近隣にいるかどうかも含めて、状況は千差万別である。産後のホルモンバランスの乱れは自力でコントロールできるものではなく、産後うつを発症する可能性は誰もが持っている。現在は産後ケア事業も発展しており、宿泊型、デイケア型、居宅訪問型の3つの形態が用意されている。利用方法やサービス内容は居住区により異なるため、出産前に自分が利用できる事業を調べておくことが大切だ。
産後うつがもたらす症状は、人により異なる。原因についても、産褥期の母親にまつわる体調不良、育児環境やストレスの根本原因、幼少期の家庭環境など、複合的な要因が絡み合っている。よって、何らかの事件が起きた際、公に報道される限られた情報の中で、他人である私たちが「原因を解明する」ことなど不可能だ。
周産期のこころの医学に精通している医師の村上寛氏による著書『さよなら、産後うつ』(晶文社)に、こんな一節がある。
今、目の前の育児に関して妊産婦さんに何か声をかける際は、できる限り「妊産婦さんのこれまでの努力」に目を向けることが大切です。
(村上寛(2021)『さよなら、産後うつ』、晶文社、 P109より引用)
道を踏み外す人の多くは、意思が弱いのではなく、むしろ強すぎるほどの忍耐力と責任感に縛られている。安全圏から石を投げる者たちは、事が起きるまでその人がどれだけ必死に闘ってきたか、その間どれだけ孤独だったか、そこに思いを馳せることはない。
見聞きするだけで胸が詰まるような事案が、これまでも幾度となく繰り返されてきた。そのたびに、母親が孤独に苛まれながら育児を担う危険性が叫ばれている。しかし、一時保育は待機が連なり、ベビーシッターは高額で市井の人々には手が届かず、行政の支援は常にマンパワー不足で、頼みの綱である父親は仕事を休むハードルが高い。命が何度奪われようと変わらない現実の中で、親たちは日々足掻いている。
間に合わせたい。間に合ってくれ。そう願い、駆けずり回る人たちがいる一方で、救いを求める声と手を差し伸べる側の数があまりに不均衡なのが現実だ。育児に悩む母親に必要なのは、一過性の寄り添いや思いやりではない。継続的かつ実質的な育児支援と、病気への理解促進、適切な治療と休養である。同時に、母親に対するケアだけでなく、支える側の父親のケアもあわせて必要なことはあまり知られていない。