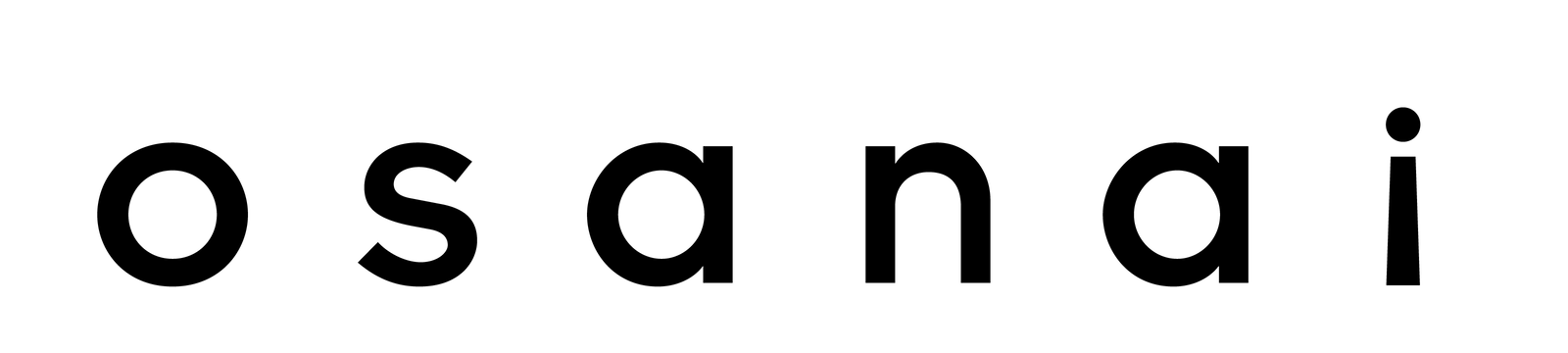変化を恐れる人々は、「考える人」を排斥する。その先の未来が明るいものであるならばいい。だが、そうは思えないから声を上げる人たちがいて、フェミニストはその先端をいく。
男女間における権利の不平等に対する抵抗としてはじまったフェミニズムは、現代ではさらに幅広い意味を持つようになった。社会が求める「男らしさ」に縛られ、生きづらさを感じる男性、ジェンダーマイノリティゆえの差別に苦しむ人々など、ジェンダー問わず多様な人々が自由と人権を求めて声を上げている。フェミニズムが求めるものは、理不尽な制約からの解放と尊厳の遵守である。決して男女を分断するようなものではなく、むやみに恐れる必要はない。
本書においても、「虎に翼」に登場する花岡や轟太一が、「男らしさ」の呪いから解放される過程について綴られている。「強くあれ」「優秀であれ」「家を守れ」といった呪いのほかに、もうひとつ呪いが存在すると著者は語る。
「心を見つめて言語化することは“男らしく”ないことだから、そんなことはするな」というものもあるのかもしれない。
(西森路代(2025)『あらがうドラマ 「わたし」とつながる物語』、303BOOKS、P228より引用)
自身の心情に目をこらし、内在する生きづらさを詳らかに語る。その過程を経てはじめて見えてくるものがあるのに、それ自体を否定されるのはさぞ窮屈だろう。このように、本書ではドラマを通して多様なフェミニズムのあり方が提示されている。
私は日頃、それほど多くのドラマを視聴しているわけではないが、野木亜紀子脚本のドラマは可能な限り観るようにしている。野木さんがつくるドラマは、厳しいのに温かい。本書にある以下の一節は、私の中にある野木作品への信頼と深く重なった。
しかし、野木作品で共通しているのは、そのような加害性があったとしても、一発でアウトにはならないということだ。(中略)
(西森路代(2025)『あらがうドラマ 「わたし」とつながる物語』、303BOOKS、P147〜148より引用)
これは、人の「内心」には、誰にでもそのような加害性があって当然で、それは、出会いや対話によって、改めることができるということが前提としてあるように感じる。
野木作品には、大なり小なり「加害者」と「被害者」が存在する。だが、その関係性は些細なことで反転するし、加害者が「完全悪」として描かれることもない。誰しもが加害者になり得るし、どんな人の中にも差別意識は存在する。その前提を持ってして、「それでも加害や差別を許さない」という確固たる意思を感じるところに信頼を覚える。
誰もが不完全だからといって、人を傷つける行いを許容してはならない。不完全だからこそ、私たちは学ぶべきだし、人を傷つけることを減らす努力をするべきだ。そんなメッセージを受けとれるのが野木作品であり、その「あらがう」姿勢からいつも揺るぎない力をもらっている。