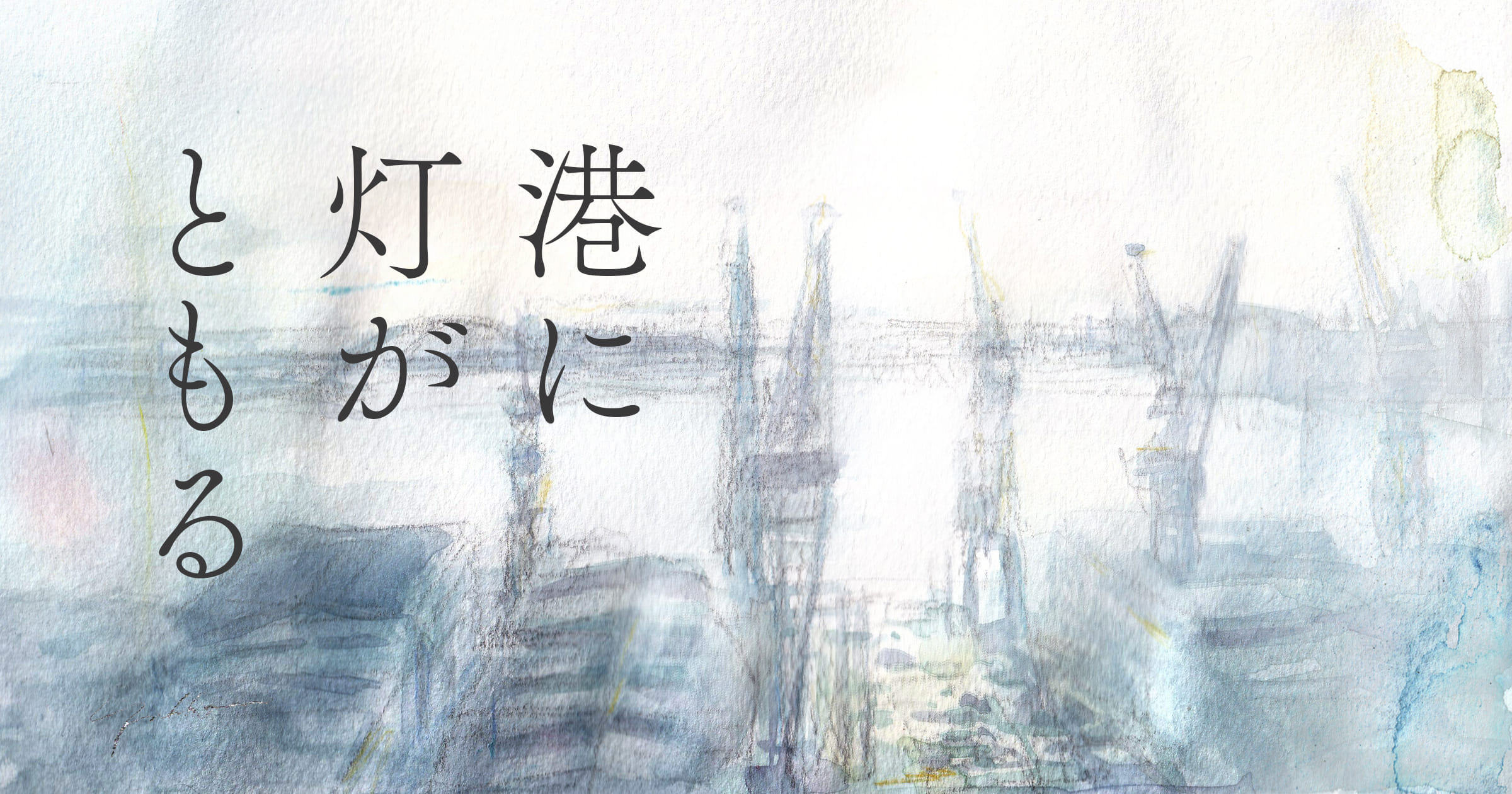1995年の震災で甚大な被害を受けた神戸市長田区。物心がつく前に震災を経験した金子灯は、両親から震災当時の話を聞かされても実感を持てずにいた。
NHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」や映画「心の傷を癒すということ」を手掛けた安達もじりが監督を務める。富田望生が主人公・灯を演じている。
──
1995年1月17日早朝、阪神・淡路大震災が発生し、大勢の人々が命を落とした。あの日から30年が過ぎた2025年同日、震災後の神戸に生きる人々の姿を描いた映画「港に灯がともる」が公開となった。復興とは、家族とは、生きるとは。数々のテーマを内包した本作で描かれる景色は、ほのかな光と暗闇が同居する。
主人公の金子灯は、震災直後の神戸で生まれた。在日韓国人3世で、両親の不仲と父親の高圧的な物言いに圧迫感を抱いていた彼女は、就職後ほどなくして双極性障害を発症する。症状が悪化し、仕事に行けなくなった灯は、社員寮から実家に戻り、療養生活を送る。だが、家族の理解を得ることは難しく、特に姉は辛辣な物言いで灯に再就職を促す。
自己嫌悪に陥り、余計に塞ぎ込む灯だったが、友人の勧めで出会った主治医との対話を重ねる中で、少しずつ心を開放していく。
「金子さんがどう感じたか。それが正解でいいんです」
つらい、苦しい、悲しい、嬉しい。何をどう感じるかを決められるのは本人だけで、それを「正解」と思っていい。そう言い切る精神科医の言葉は、当事者にとって大きな救いである。人の感情は、他者がコントロールできるものではない。そんな当たり前のバウンダリーは、時に悪意なく侵害される。灯の感情の発露を「甘え」と切り捨てるのは容易いが、その接し方が患者の心を楽にすることは決してない。
「働かない」ではなく「働けない」のだと、周囲に理解してもらうことは時に困難を極める。家族であっても、いや、家族だからこそ理解されない、分かり合えないケースも多い。朝から晩まで布団に横たわる精神疾患者は、外側からは「怠けている」ように見られることがある。実際は、脳内で休む間もなく思考を巡らし、思考に追いつかない体の倦怠感に怯え、日がな1日自責の念に駆られて苦しんでいたとしても、その葛藤は外側からは見えないのだ。
震災直後に生まれた灯は、当時の大変な状況を繰り返し聞かされて育った。震災当時、出産直後の母を置いて、父は実母の元に駆けつけた。そのことを母は根に持っており、折に触れて恨み言を口にする。その出来事がきっかけで夫婦仲が壊れてしまったのだと幼い時分から聞かされれば、灯が自身の存在を否定するのもむべなるかなと思われる。
震災そのものの記憶はなくとも、両親から浴びせられる言葉の端々から情景を想像し、「大変だった」事実と「自分が生まれてきたせいで」という自責が結びついた結果、「生まれてこなければよかった」とまで思い詰めた灯。そんな彼女の傷は、震災被害による余波のひとつといえるのではないだろうか。