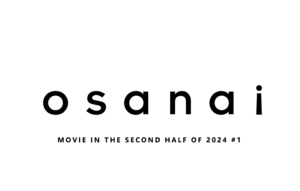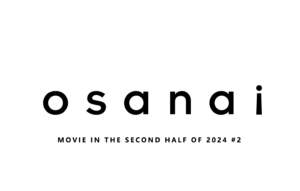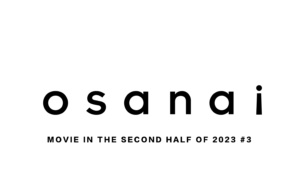言葉が“何”をしたかを知ること
物語が終盤に差し掛かると、「血を流さずに日本を勝利に導ける」と意気込んだ館野は実際に戦地へ足を運ぶことになる。そこで見た死体の山に、悲劇に、彼は泣き崩れた。
声高らかに「一億玉砕せよ!」と言った口で、何度も何度も謝罪する。「ごめんなさい。言葉はなんの役にも立ちませんでした」。
実をいうとわたしはこの謝罪がとても嫌だった。謝ってももう遅いと思った。役に立つとはどの状態のことを指すんだと思った。その謝罪だって、なにも考えずに言ってるだけじゃないのか。だからあなたの言葉は無力なんじゃないか。なぜだか悔しかった。
作家さんとの手紙のやりとりを思い出しながら、わたしは館野を当時の自分と重ねていたのだろう。わたしが館野で、作家さんが和田。わたしはずっと、和田になりたいと思いながら観ていたのだ。
「虫眼鏡で調べて望遠鏡で喋る」をモットーとする和田には伝説の放送がある。第一次世界大戦で殉職した死者を弔う招魂祭だ。「母さん、母さん。元気かい」からはじまるその声は、綿密な取材を重ねた上で創作されており、まるで憑依した死者が手紙を読んでいるようだった。これぞぴかぴかの剣を持つ者だと思った。
物語が後半に進むと、和田は戦地へ向かう若者の声を聞くことを決める。出会った野球少年らは、戦地へ行くことについて明るい声で「明日にでもいけますよ!」「光栄です!」などと言う。だが和田はそのテンションに乗らない。君たちの本音が聞きたいと訴える。
すると少しずつ、ぽつりぽつりと「死にたくない」「野球がしたい」という声が漏れる。中には「アナウンサーになりたかった」という少年もいた。
こんなことがわたしにできるだろうかと思った。もしも自分が和田の立場なら、死にに行くと分かっている若者の顔を、性格を、夢を知りたくない。存在する人間だと理解したくない。知ったところで自分は「玉砕せよ」と言わなければならないのだ。すべてを知った上で何もできない苦痛に耐えられる気がしない。
実際のところ、和田はその苦痛に耐えられたわけではなかった。終盤は壊れてしまいそうだった。
想像できたはずだ。心のどこかでは知っていたはずなのだ。なのにわざわざ会いに行き、確かめた。キャッチボールにまで参加して、少しの人間関係を育みもした。
和田がそうしたのは、取材でも興味でもないと思った。知らなければいけないと思ったのではないか。自分が言葉で“何”をしているのかを。
館野が戦地で涙を流したのも、自分の言葉が何を隠蔽してきたのかを知ったからだと思った。もしも彼が先にこの現状を目の当たりにしていたら、「玉砕」という言葉を美しいとは感じなかっただろう。
作家さんが教えてくれたように、言葉は剣なのだと思った。使い方を間違えれば簡単に人を傷つけてしまうからこそ、生半可な気持ちで取り扱ってはいけないのだ。