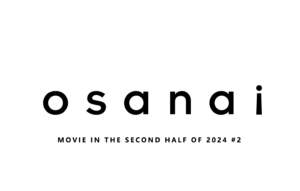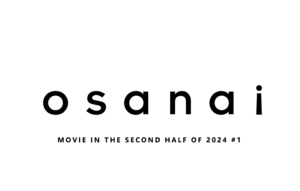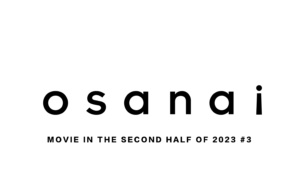もう少し映画を思い出してみたい。
日本への原爆投下後、ロスアラモスの住民に向けてオッペンハイマーがスピーチを行う場面。オッペンハイマーは町民たちを、文字通り爆発的な歓喜に巻き込むが、どうやら自身の思いは別のようだ。町民が消え、被爆者の幻影が現れ、歓声が原子爆弾の爆風に負けない音量で流れる中で、彼は激しく後悔していたように見える。
つまり、オッペンハイマーという人物は、発言と実際の中身が全く異なる人物だったのではないか。そして、そのズレに誰からも気づかれることなく生涯を終えてしまった人物なのではないか。
それでも、求められれば何だってする。自分が心の底から望んでいないことでも。オッペンハイマーは、もしかしたら頼まれ仕事をする天才だったのかもしれない。
本作を見る限り、オッペンハイマーが心の底から実現したかったことなど存在しないように見える。頼まれ仕事の積み重ねで歴史に名を刻んでしまったのではないか。オッペンハイマーの並外れた天才性が、周囲との乖離を生み、最終的に自分を窮地に追い込んでしまったのではないか。
マンハッタン計画さえ、オッペンハイマーにとっては頼まれ仕事の一部だったのかもしれない。もちろん、最初こそナチスへの対策として、ユダヤ人である自分の使命として参加を決意したのだろう。彼の発言に嘘はなかったはずだ。
しかし、ナチス降伏後も、なぜか開発を継続してしまう。自身が熱心に立ち上げた大学内の労働組合はあっさりと畳んでしまうのに。「熱心に」振る舞っていても、本心は別だったのかもしれない。頼まれ仕事こそ彼の存在意義だったのかもしれない。
敵対したエドワード・テラーが
「J・ロバート・オッペンハイマー、謎めいた原始の教祖。あなたが信じていることを誰も知らない。そうだろう」
(「オッペンハイマー」脚本 P151より筆者訳)
と発言していたことも思い出される。
だからこそ、頼まれ仕事ばかりこなしているオッペンハイマーが欲求不満となり浮名を流しても、人間として当然だったのかもしれない。オッペンハイマーも人間だったのか、と安心すべきシーンだったのかもしれない。