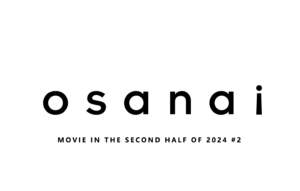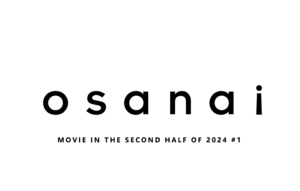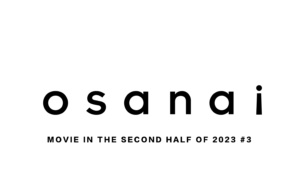「落下の解剖学」の本当の被害者
人里離れた雪山の山荘で転落事件が起き、妻のサンドラは夫の殺害容疑をかけられる。当時家に居たのはサンドラと愛犬のほか、視覚障がいをもつ息子のダニエルだけだった。
今作の見どころは事件の真相よりも、周囲からは仲のいい夫婦と思われていた2人の実際の関係が、音声記録や証言から明らかになっていく点だ。
そして、11歳のダニエルが、父親と母親の不仲にまきこまれてしまったことこそが悲劇だった。
ダニエルはある記憶から、母親が父親を殺した可能性を捨てきれずにいた。そして、ダニエルの証言が裁判でカギを握る局面になり、その記憶を語るのか母親をかばうのか、究極の選択を迫られる。
彼は大人になってからその証言を悔やむかもしれない。その後悔が、彼の人生観をゆがめてしまうことも十分ありうる。
サンドラが夫を本当に殺したのかどうかよりも、息子に対してそんな重責を担わせてしまったことが罪深い。この事件の一番の被害者は、ダニエルだ。
「システム・クラッシャー」ベニーが向かう破滅の道
赤ん坊のころに、父親から顔におむつを押し付けられたことで、トラウマを抱えている9歳の少女ベニーを追った、ドイツ発のヒューマンドラマ。
ドキュメンタリーと錯覚するような映像と、ベニー役のヘレナ・ツェンゲルの演技がすさまじく、何度も繰り返される彼女の叫び声が脳裏に焼きつく作品だ。
ベニーは気に入らないことがあると、自制がきかずわめき散らして暴力をふるってしまうため里親やグループホーム、支援学校のどこにも居場所がなくなっていく。
そこで、通学付添人の男性ミヒャが、山奥の山荘で3週間の隔離療法を提案する。ベニーはミヒャに少しずつ信頼を寄せるようになるのだが、問題は解決しなかった。
ミヒャの他に手を差し伸べたのは、社会福祉課のマリアだ。問題を起こすたびにベニーを守ろうと奔走していた。ようやく母親がベニーを引き取ることが決まったものの、土壇場になって母親が拒否したことで、ベニーよりも先に絶望で泣き崩れたのはマリアだった。
ベニーをシステム・クラッシャーにしたのは、トラウマを植え付けた父親であり、諦めずに寄り添えなかった母親の責任でもある。
大人が生み出したクラッシャーを、大人が救おうとするが叶わない。そんな絶望が充満する世界で、子どもはどうやって生きていったらいいのだろう。
山の中をさまようベニーが保護された後の(ここで隠喩のような場面が挿入される)ラストシーンでベニーは空港を爽快に走りまわる。
このシーンで私は、グザヴィエ・ドラン監督の「Mommy/マミー」を想起した。スティーブは精神病棟で看守の目を盗み、走り出す。母親に最後の電話をしたあと、死に向かったのだと解釈することができる。そのシーンに使われているラナ・デル・レイの楽曲「Born To Die」の「私たちは死ぬために生まれたの」という歌詞がそれを印象付けていた。
駆けまわるベニーを待つのは破滅の道なのか?そうは思いたくないが、その可能性を匂わせている気がしてならなかった。