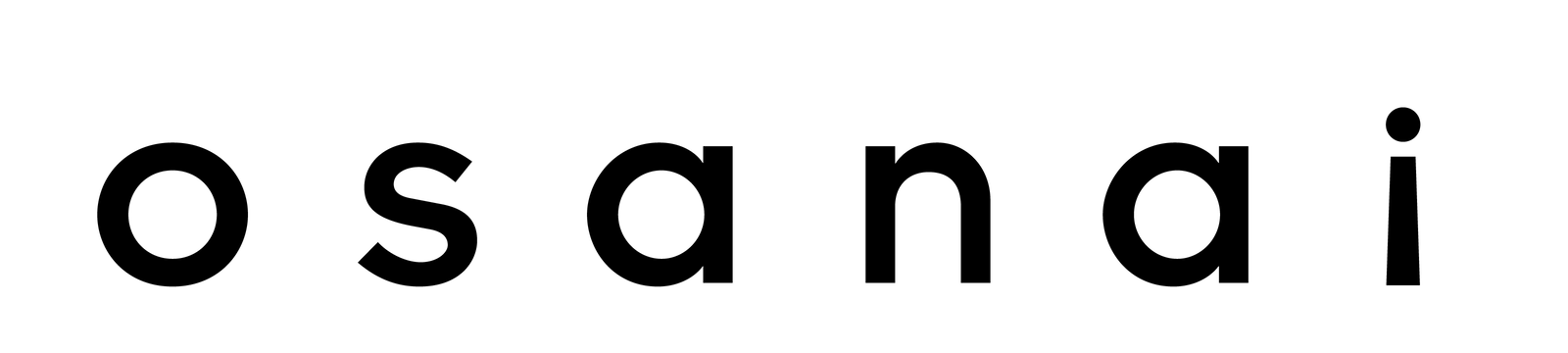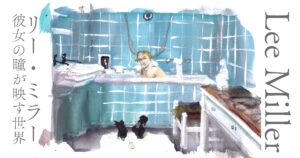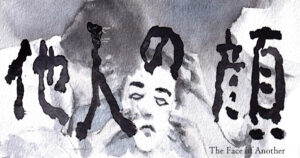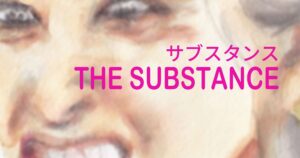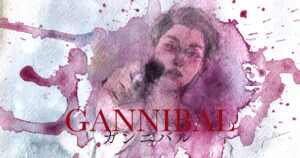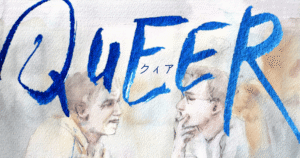「許さない」の先にあるもの
最後に、ヴィクターは創造主である自分の責任を認めて、「彼」に謝罪をし、生きろと伝える。そして、「彼」はヴィクターを許す。「英知とは、許す(forgive)ことと忘れる(forget)ことだ」という老人の言葉がよぎる。美しいシーンだった。グッとくるところがあった。
しかし、映画を見た後に改めて原作を読んで、本当にこのラストでよかったのだろうかという思いが湧いてきた。
原作のラストでは、ヴィクターが亡くなった後に「彼」は船に辿り着く。そして、対話の代わりに、長い独白をする。
自分が犯した恐ろしい罪をひとつひとつ思い返してみると、われながら信じられない気持ちになる。至高の美や絶対的な善に胸を震わせていたかつての自分と、これが同じものなのか、とな。いや、そうなのだ、堕ちた天使は悪辣な悪魔になると言うだろう?しかし、そんな神と人間の敵でさえ、寂寥を慰めあう友がいる。なのに、おれは独りだ、独りきりなのだ。
おまえは確かに打ちのめされた。だが、俺の苦しみはそれよりも深い。悔恨の鋭い棘が傷を疼かせ、その痛みは死が傷口を塞ぐまで続くのだから。
「彼」の独白を聞いて、僕は自分が消費的な見方をしているような感覚に陥った。「許し」という行為を、そこに内在する美しさを消費しているのではないかと。
エゴで生み出し、何のケアもせず、憎しみをぶつけ、要望は聞かない。そんな人間が最後の最後に悔いる姿を見て、本当に許すことはできるのだろうか。いや、できる人はいるのだろう。世界のどこかには。でも、もし僕が「彼」だったら?絶対に許さないだろう。最後に許されたいだなんてエゴイストにもほどがある、拒絶されたまま死んでいけ、くらい思うかもしれない。
許すことを描くことの大事さもわかる。特に、深い分断が生まれている今の時代に、原作の終わり方は救いがなさすぎる。でも、「彼」はこれからトラウマや怒り、そして罪を抱えて、「彼」をケアする人が一人もいない世界で生きていくのだ。その困難さを、許すという行為の後光で見えなくさせてしまう、希望という言葉で包んで隠してしまうのは、あまりにも都合が良すぎるというか、消費的あるいは啓蒙的にすぎるのではないだろうか。
原作小説では、エピグラフとして冒頭に以下の文言が引用されている。
創造主よ、私を土塊から人の姿に創ってくれと頼んだことがあったか?わたしを暗黒から起こしてくれと願ったことがあったか?(「失楽園」第十巻)
「彼」がヴィクターへの憎しみを手放して、それでも許さずに自分の人生を生きていく。そんなことができるのかはわからない。できない気もする。でも、できてほしい。製造物に責任を負わない存在の許しなんてなくても生きていけることを示してほしい。それこそが希望なのではないかと思う。
──
■フランケンシュタイン(原題:Frankenstein)
監督:ギレルモ・デル・トロ
原作:M・シェリー『フランケンシュタイン』
脚本:ギレルモ・デル・トロ
撮影:ダン・ローストセン
美術:タマラ・デヴェレル
衣装:ケイト・ホーリー
編集:エヴァン・シフ
視覚効果監修:デニス・ベラルディ
キャスティング:ロビン・D・クック
クリーチャーデザイン:マイク・ヒル
音楽:アレクサンドル・デスプラ
出演:オスカー・アイザック、ジェイコブ・エロルディ、ミア・ゴス、クリストフ・ヴァルツ、フェリックス・カメラーほか
配信:Netflix
公式サイト:https://www.cinemalineup2025.jp/frankensteinfilm/
(イラスト:水彩作家yukko)