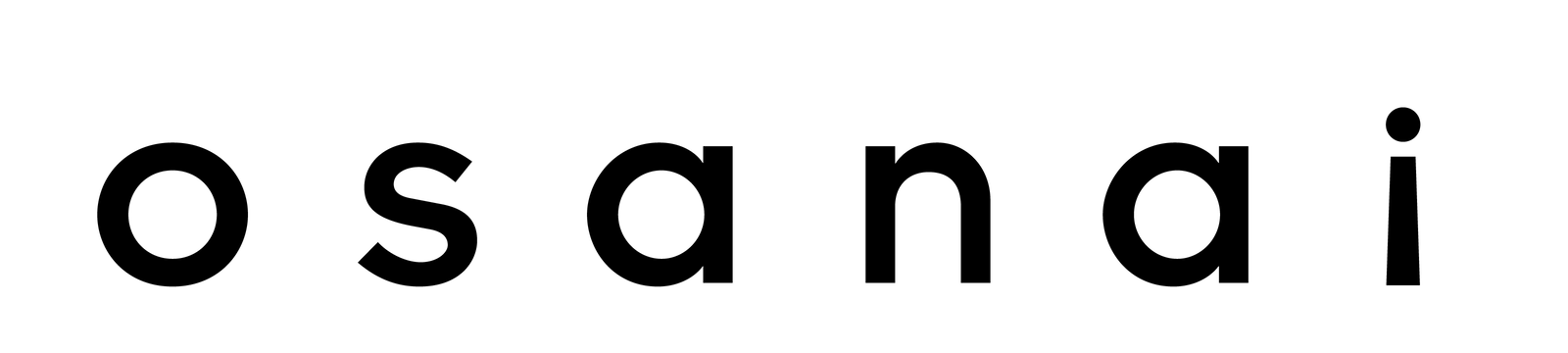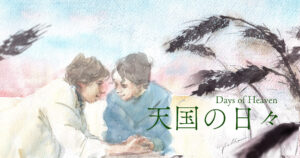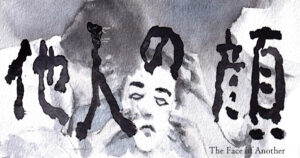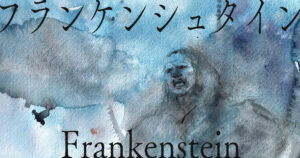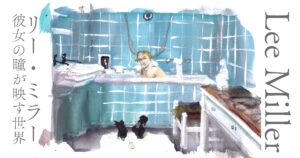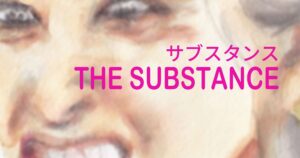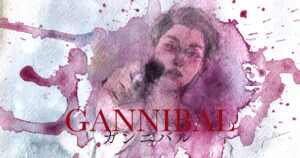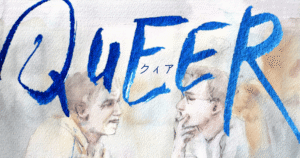「馬鹿を言っちゃいけないよ」「砂っていうのはね」
最初の晩から、日がな砂と暮らす女を相手に、男がいちいち砂の性質について講釈を垂れる。
田舎の寡婦を無知で愚鈍なものだと決めつける、インテリの傲慢さ。
そこには、男の都会で暮らす現実への不満、あるいは苛立ちが滲む。
虫を集めて個人的に研究する彼は、本当は一介の学校教師などではなく、生物学者になりたかったのかもしれない。
不運や構造、あるいは社会の曇った審美眼のせいで、いまだ自分の才能は発掘されていない、彼にはそんな欝々たる気持ちがあるのかもしれない。
砂の湿気が柱を腐らせているという事実を理屈に合わないからと否定して打ち捨てる様からは、この男の人生が十分に潤されたものとは到底思えなかった。
どちらが強いか弱いのか。どちらが支配し支配されるのか。
男の心理には、常に優劣や序列を気にせずにいられない不自由さが染みついている。
そんな男が、砂穴に閉じ込められた。
四方を囲む高い砂の壁。そこから逃れたいと思うのは本能だ。
蟻地獄にはまった蟻だって、そう簡単に自分の運命を受け入れられず、砂肌で懸命に足掻くではないか。
しかし、脱出の失敗を繰り返すうち、男はやがて砂穴での生活に安堵を見出し始める。
外界と隔絶され、一晩中砂搔きの労働を強制され、生殺与奪を他者に委ねるしかない立場。
不自由極まりないはずの環境におかれながらも、男はこの場所に来た時よりもずっと穏やかな表情を浮かべるようになるのだ。
村人とは良好な関係を築き、新聞でも筆記用具でも、要求すれば必要な物資が与えられるようになった。
その家の女とはもはや夫婦のようであり、互いに労わりの気持ちさえ芽生えている。
かつて男が持っていた職業や学歴、家族や財産、それに付随する義務、しがらみ、プライド。
そういった一切と切り離された砂の世界において、序列など無意味だ。
あるときは優位、あるときは劣位になり、他者を攻撃し他者から身を守るための刃を、ここでは捨てて構わない。
そのとき、閉じ込められた孤独は、選び取った孤独に変わる。
男は、不自由さの中で解放を得たかのようだ。