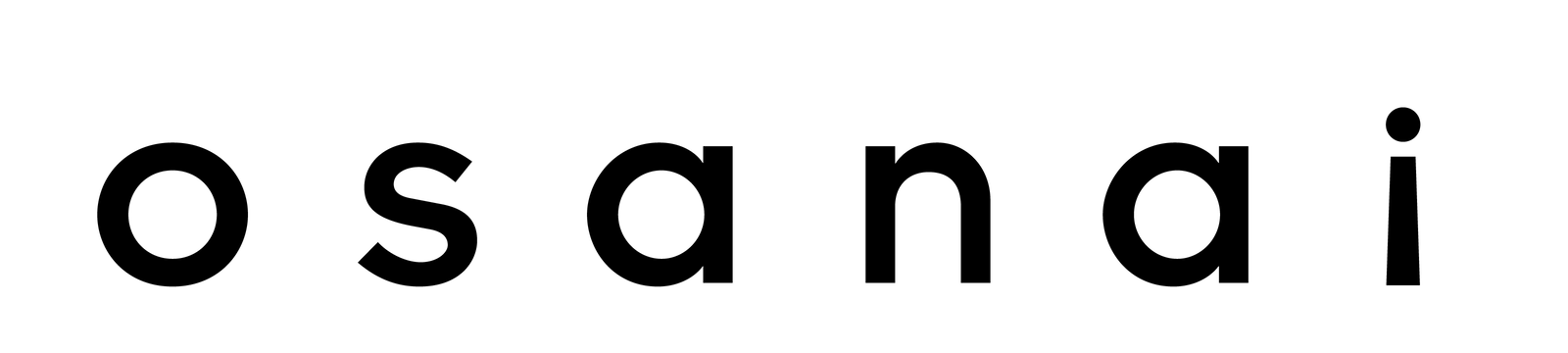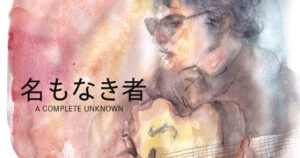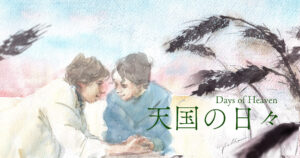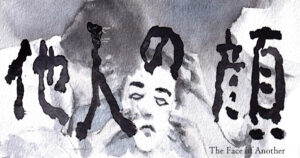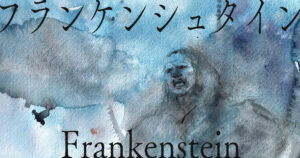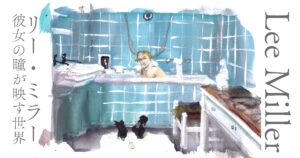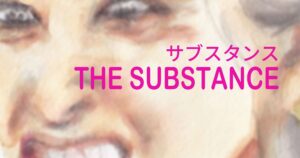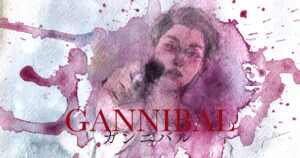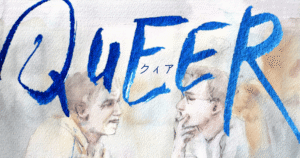カナコが、職場の先輩である吉沢にアプローチされて、彼の思いを受け止めようか迷う場面がある。
もし、カナコがカナコでなかったら、理屈や損得勘定を働かせ、吉沢の恋人にさっさとなるのだろう。だって吉沢は、長津田の言葉を借りれば「ハイスペック野郎」──つまりは長津田本人から見ても「上位互換の存在」なのだから。
でも、カナコはそうしない。どんなに長津田がダメ男かを熟知しているはずなのに、彼の影を人生から消そうとしない。そこに、この映画の味わいがあるように思う。
カナコの上司で、吉沢の元恋人の亜依子は、長らく愛用していたのにもう手に入りにくくなっていたシステム手帳を、カナコからプレゼントされる。手帳を見て、亜依子はぽつりと「替えがきかないのよね」ともらす。
しかし映画の終盤で、亜依子はカナコにならい、罫線のない真っ白なノートを初めて使う。「替えがきかないと思っていたものも、そうではなかった」と示しているシーンに思えた。
本作を見ながらずっと「替えがきく」関係と「替えがきかない」関係について、私は考え続けることになる。そして気付いたのは「替えがきくか」「きかないか」という軸の外に、カナコが求めたいものがあったのではないか、ということだ。そのヒントになるのが、カナコをめぐる女性たちの描かれ方だ。
この映画で印象的なのは、恋人をめぐる三角関係の恋敵役──麻衣子や亜依子が、最終的にはカナコと歩み寄り、心を分かち合う仲となっていることだった。
鍵を握っているのはカナコだ。たとえば、「恋敵」というレッテルを相手に貼ってしまったら、それ以外の「その人本人の事情や人となり」が見えなくなってしまうことがある。カナコは麻衣子や亜依子に「恋敵」というレッテルを貼らずに(というか、貼ろうなどと思わずに)目の前にいる一人の人間として接している。
そのあたりが、麻衣子や亜依子がカナコとの関係を、最終的に居心地よいものに感じているゆえんではないだろうか。カナコと麻衣子、カナコと亜依子の関係に、おそらく名前はつかない。けれど、映画を観ているうちに、関係を表す名前など不要と思わせられてしまう。
そして長津田との長い長い10年こそ、カナコにとって「名前のつかない」関係だった。相手を過剰に「不要」とも「必要」ともみなさない関係性。その均衡が、最後に崩れることになる。